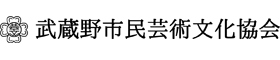令和4年10月2日 「平家物語」を語る
舞台には魔物がいた
いきなり驚いた。隣で同じ演目を朗読していた仲間の声が、本番直前の練習とは打って変わって、力強く響いてきたのだ。その声に押されるように、私は自分の役どころの第一声を語り始めた。
令和四年十月二日、武蔵野スイングホールで開かれた「平家物語」朗読教室の第七回発表会でのことである。第七〇回武蔵野市民文化祭の一環として開催されたものだ。
私たちのチームが演じたのは、「平家物語」巻第十、「千手の前」の章段だった。敵方の源氏に捕らわれ、鎌倉へ送られた平家の若き貴公子・平重衡が、死を目前にしながらも、わずかな慰めのひと時を得る場面である。重衡は、千手の前という頼朝に仕える美女と琵琶や箏の音曲を楽しみ、やがて静かに死へと赴く。
実は本番直前まで、私はかなり焦っていた。会場での直前練習では、他のチームの「那須与一」「敦盛最期」などの有名な章段を朗読する声が響いている。その中で、あまり知られていない「千手の前」が、どれほど観客に受け入れられるのだろうか。そして、この発表会はコロナの影響で三年ぶりの開催ということだったが、一年前に教室に通い始めた私にとっては初舞台なのである。
しかもだ。開演後に客席を盗み見ると、最前列のど真ん中に、私の親友が陣取っているではないか。「ちょっとお~。何でそんなところにいるのよ。目が合ったらどうすんの」と、思わず胸のうちで舌打ちをした。 だが、いざ本番が始まってみると、私の頭からは全てが消えた。ただもう、物語の世界に引きずり込まれていったのだ。舞台には確かに魔物がいる。そんな思いが胸によぎった。
「平家物語」は、とにかく全編が長い。言葉も難解である。ただ、その難解さに捕らわれるのではなく、役どころの人物の思いを、自分の思いに重ねて訴えることで見る人の心に届く、と教えてくれたのは、師匠であり俳優の、金子あいさんだった。その言葉にすがり、私は夢中で語り続けた。
終演後の興奮も冷めやらぬまま、「次は一年後かあ~」と、私はひそかに次の舞台を心待ちにしている。
「平家物語」を語る会 中村貴美江